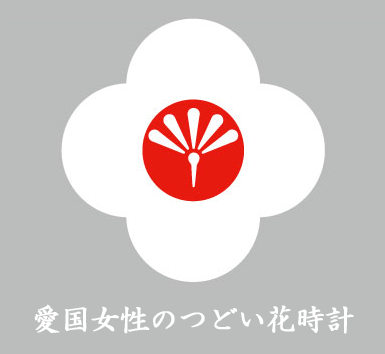司法の闇について Q&A
最近、裁判のニュースが増えたような気がしますが?
「裁判員制度」が導入されて以来、ニュースに裁判が頻繁に取り上げられるようになりました。このこと自体に違和感を覚える人もいるかと思いますが、判決の内容にも首を傾げることが時々あります。裁判所などという場所は一般の国民にとっては縁遠いところだと昔は思われていました。できれば一生、関わりたくないと多くの人が思っているでしょう。日本人はもともと裁判に訴えてもめ事を解決するなどということは好みませんでした。もめ事が起きてもできるだけ話し合って妥協点を見つけ、譲り合って解決してきたのです。裁判に訴えれば一方が勝ち、一方が必ず負けます。しかし、社会のさまざまな問題は複雑で多面的なものなので、単純に勝ち負けで決着をつけられないこともあります。無理に決着をつけたからといって、それで双方が納得できるかといえば、それも難しいです。ですから、できれば裁判などに訴えないで解決する道を探った方が良いのです。
しかしさまざまな事情で「裁判員制度」が導入された今、私たちは好むと好まざるとに関わらず、以前よりも裁判に関心を持たざるを得なくなりました。ある日突然、私たちが裁判員に選ばれるかも知れないのです。裁判というものについて、また法廷で向き合うことになるかも知れない裁判官という人たちについて、もはや無関心ではいられなくなってしまいました。
しかしさまざまな事情で「裁判員制度」が導入された今、私たちは好むと好まざるとに関わらず、以前よりも裁判に関心を持たざるを得なくなりました。ある日突然、私たちが裁判員に選ばれるかも知れないのです。裁判というものについて、また法廷で向き合うことになるかも知れない裁判官という人たちについて、もはや無関心ではいられなくなってしまいました。
なぜ裁判官は非常識なのですか?
『裁判官が日本を滅ぼす』(門田隆将著・新潮文庫)という本があります。題名の通り、さまざまな裁判の事例を取り上げて、裁判官がいかに非常識で世間知らずで「真実」や「正義」とは程遠いところにいる人たちなのか、ということを描いた本です。例えば極悪非道の強姦殺人犯を無罪にした裁判官、鑑定の虚偽を見抜けない無知な裁判官、勇気を出して会社を内部告発した人を罰した裁判官・・・もちろん、まともな裁判官もたくさんいるのでしょうが、それにしてもこんな人たちが法廷を仕切っているとは怖ろしいことです。
トンデモ判決を出す裁判官に共通しているのは「判例主義」「相場主義」です。個々の事件の事情や背景を細かく検証することなく、過去の同じような事件の判例に従ってただ機械的に判決を出しているだけなのです。例えば殺人の場合、被害者が一人であればどんなに残虐な殺し方をしてもまず死刑判決は出ないというのが「相場」だそうです。本来、日本の法律は量刑の範囲が広く、殺人に対する刑罰は懲役3年から死刑まで選べます。裁判官は量刑を選ぶ権限があるにもかかわらず、実際には相場に従った似たような判決しか出さないのです。なぜそうなるのでしょうか?
裁判官には「事実認定」と「量刑判断」の権限があります。「事実認定」は法廷に出された証拠から一つ、一つの事実があったのか、なかったのか、やったのか、やらなかったのかを決めることです。裁判官は司法修習生時代に「事実認定」のやり方を徹底的に叩きこまれます。過去の事件の記録をもとに「こういう証拠は採用していい」「こういう証拠は採用してはいけない」という原則を機械的に覚えこまされているうちに人間性や常識を失っていくのです。
司法の世界は最高裁判所を頂点にして全国に8か所の高等裁判所、50か所の地方・家庭裁判所、438か所の簡易裁判所で構成されています。普通、裁判官になって15年もすると自分はエリートコースに乗れたのか、外れたのか、分かるそうです。裁判官になっても高裁長官や最高裁判事になれるのはほんの一握りの人です。出世するためには上級庁の意向に逆らってはいけません。だから裁判官は個々の訴訟の中身よりもただ手際よく、無難な判決を出すことだけを考えて審理に当たるのです。
トンデモ判決を出す裁判官に共通しているのは「判例主義」「相場主義」です。個々の事件の事情や背景を細かく検証することなく、過去の同じような事件の判例に従ってただ機械的に判決を出しているだけなのです。例えば殺人の場合、被害者が一人であればどんなに残虐な殺し方をしてもまず死刑判決は出ないというのが「相場」だそうです。本来、日本の法律は量刑の範囲が広く、殺人に対する刑罰は懲役3年から死刑まで選べます。裁判官は量刑を選ぶ権限があるにもかかわらず、実際には相場に従った似たような判決しか出さないのです。なぜそうなるのでしょうか?
裁判官には「事実認定」と「量刑判断」の権限があります。「事実認定」は法廷に出された証拠から一つ、一つの事実があったのか、なかったのか、やったのか、やらなかったのかを決めることです。裁判官は司法修習生時代に「事実認定」のやり方を徹底的に叩きこまれます。過去の事件の記録をもとに「こういう証拠は採用していい」「こういう証拠は採用してはいけない」という原則を機械的に覚えこまされているうちに人間性や常識を失っていくのです。
司法の世界は最高裁判所を頂点にして全国に8か所の高等裁判所、50か所の地方・家庭裁判所、438か所の簡易裁判所で構成されています。普通、裁判官になって15年もすると自分はエリートコースに乗れたのか、外れたのか、分かるそうです。裁判官になっても高裁長官や最高裁判事になれるのはほんの一握りの人です。出世するためには上級庁の意向に逆らってはいけません。だから裁判官は個々の訴訟の中身よりもただ手際よく、無難な判決を出すことだけを考えて審理に当たるのです。
日本の少年審判は不可解なものが多いような気がしますが?
最近、少年による凶悪犯罪が増えています。体は大人でも精神的には未熟な少年が犯す犯罪は、大人による犯罪よりも時には凶悪です。にもかかわらず犯人が19歳以下なら実名報道もされず、検察にも送られず、つまり刑事裁判が行なわれることもなく家庭裁判所から少年院に送られるケースが多いのです。少年院に送られても、実際には2年以内に少年院を出て社会復帰することが可能です。
2001年、滋賀県大津市で痛ましい事件が起きました。左半身が不自由な16歳の障害者が15歳と17歳の少年によって惨殺されたのです。被害者は15歳の時に交通事故に遭い、脳死状態から奇跡的に助かり、リハビリで何とか歩けるようになりました。リハビリをしながら定時制高校に通っていましたが、大学に行きたくて全日制高校を受験、合格したばかりでした。障害者でありながら持ち前の頑張りで難関の高校に合格した少年を妬んだ不良少年による犯行でした。抵抗できない障害者をリンチで殺した二人の少年に対して裁判長はなんと中等少年院送致という甘い処分を下したのです。
犯人が少年でも18歳以上なら法律上、死刑は認められています。しかし実際には少年審判で死刑判決が出ることはほとんどありません。また少年法61条の規定によってマスコミは犯人の実名や顔写真を報じません。つまり19歳以下というだけで殺人をしたり性犯罪を犯しても周囲の人にまったく知られることなくまた社会復帰できるわけです。果たしてこれで社会の治安が保てるのでしょうか?
少年法の精神は1899年にアメリカのイリノイ州で始まった「国親思想」によるものです。貧乏で親もなく、非行に走る少年を親に代わって国が更生させるという考え方です。アメリカの少年法をモデルに日本では1947年に少年法が制定されました。当時は敗戦後の混乱期で戦争で親を失った子供や貧しさから犯罪に走る子供も確かにいたでしょう。しかし時代は変わりました。今では少年法を盾にとって「19歳以下なら死刑にならないから」犯罪を犯す者もいるのです。そして少年とは無垢で純粋で、悪くなったのは社会のせいだというステレオタイプの発想で判決を下す裁判官が少なくありません。これではますます少年犯罪が増えるだけではないでしょうか?
2001年、滋賀県大津市で痛ましい事件が起きました。左半身が不自由な16歳の障害者が15歳と17歳の少年によって惨殺されたのです。被害者は15歳の時に交通事故に遭い、脳死状態から奇跡的に助かり、リハビリで何とか歩けるようになりました。リハビリをしながら定時制高校に通っていましたが、大学に行きたくて全日制高校を受験、合格したばかりでした。障害者でありながら持ち前の頑張りで難関の高校に合格した少年を妬んだ不良少年による犯行でした。抵抗できない障害者をリンチで殺した二人の少年に対して裁判長はなんと中等少年院送致という甘い処分を下したのです。
犯人が少年でも18歳以上なら法律上、死刑は認められています。しかし実際には少年審判で死刑判決が出ることはほとんどありません。また少年法61条の規定によってマスコミは犯人の実名や顔写真を報じません。つまり19歳以下というだけで殺人をしたり性犯罪を犯しても周囲の人にまったく知られることなくまた社会復帰できるわけです。果たしてこれで社会の治安が保てるのでしょうか?
少年法の精神は1899年にアメリカのイリノイ州で始まった「国親思想」によるものです。貧乏で親もなく、非行に走る少年を親に代わって国が更生させるという考え方です。アメリカの少年法をモデルに日本では1947年に少年法が制定されました。当時は敗戦後の混乱期で戦争で親を失った子供や貧しさから犯罪に走る子供も確かにいたでしょう。しかし時代は変わりました。今では少年法を盾にとって「19歳以下なら死刑にならないから」犯罪を犯す者もいるのです。そして少年とは無垢で純粋で、悪くなったのは社会のせいだというステレオタイプの発想で判決を下す裁判官が少なくありません。これではますます少年犯罪が増えるだけではないでしょうか?
「医療裁判」で患者側が勝つことはほとんどないそうですね?
病気を治したくて入院したのに、入院中の事故や手術ミスによって肉親を失くした人はかなりの数いると思われます。身近にそういう話を聞くからです。しかし、そのような場合、病院側から納得のいく説明を受けることはほとんどありません。どうしても納得できない被害者や遺族はしばしば病院を相手どって訴訟を起こします。賠償金をもらいたいというよりも真実を明らかにし、謝罪してもらいたいからです。しかし「医療裁判」で患者側が勝てる見込みはほとんどありません。病院側が事実とは違う主張をしたとしても裁判官にはそれを見抜く力がないからです。
裁判官は医療に関しては素人です。また大学病院などは医療免許を持つ弁護士を顧問弁護士にしており、弁護団を組んで訴訟に臨んできます。それに対して患者側は費用の問題もあり、弁護団を組むことなどできません。裁判官は権威に弱いので「単なる一個人」に過ぎない患者の言い分より病院の言い分を認めてしまうのです。
同じことは「金融裁判」にも言えます。バブル時代、銀行はあり余った資金を貸したいばっかりに詐欺まがいの手口で融資をしていました。銀行にだまされ、担保にした自宅を奪われた人はどれほどいたでしょうか? しかし銀行を相手どって訴訟を起こしてもほとんど勝てません。裁判官にとって退官後、銀行の顧問弁護士におさまるのは最高の花道です。訴えられた銀行の顧問弁護士とたまたま個人的なつながりがある裁判官もいるでしょう。裁判官が被害者の痛みや苦しみを分かってくれるなどと期待するのは空しい幻想なのです。
裁判官は医療に関しては素人です。また大学病院などは医療免許を持つ弁護士を顧問弁護士にしており、弁護団を組んで訴訟に臨んできます。それに対して患者側は費用の問題もあり、弁護団を組むことなどできません。裁判官は権威に弱いので「単なる一個人」に過ぎない患者の言い分より病院の言い分を認めてしまうのです。
同じことは「金融裁判」にも言えます。バブル時代、銀行はあり余った資金を貸したいばっかりに詐欺まがいの手口で融資をしていました。銀行にだまされ、担保にした自宅を奪われた人はどれほどいたでしょうか? しかし銀行を相手どって訴訟を起こしてもほとんど勝てません。裁判官にとって退官後、銀行の顧問弁護士におさまるのは最高の花道です。訴えられた銀行の顧問弁護士とたまたま個人的なつながりがある裁判官もいるでしょう。裁判官が被害者の痛みや苦しみを分かってくれるなどと期待するのは空しい幻想なのです。
なぜ日本では加害者の人権ばかりが保護されるのですか?
戦後の日本社会では加害者の人権は過保護なまでに守られるのに、もっとも辛い思いをした、何の罪もない被害者の人権が無視されるという異常な事態が続いてきました。「日本弁護士連合会(日弁連)」とそれを支持するマスコミによっていつの間にか犯罪者の人権こそ守られなければならないという風潮が作られたからです。そんな状況を変えるきっかけになったのは1999年に山口県で起きた「光市母子殺害事件」でした。
23歳の主婦が強姦され、生後11か月の幼児が18歳の男に惨殺されたこの事件は社会に衝撃を与えました。犯人が少年で被害者が2人なので一審、二審とも判決は無期懲役でした。しかし判決に納得できなかった遺族の本村洋氏の執念の闘いによって9年後、少年に死刑判決が下されました。また被害者の人権も大きく改善されることになったのです。
当時は法廷に被害者の遺影を持ち込むこともできず、遺族が意見を言うこともできませんでした。裁判とは裁判官と検察と被告がやるもので法廷では遺族は完全に部外者扱いでした。しかし「光市母子殺害事件」をきっかけに「全国犯罪被害者の会(あすの会)」ができ、全国に支援の輪が広がりました。2000年には遺族傍聴席の確保、公判記録を閲覧・コピーする権利、公判での意見陳述権を認めた「犯罪被害者保護法」が成立しました。
2003年7月、「あすの会」代表は39万63人の署名を持って小泉純一郎首相に面会しました。小泉首相のリーダーシップの下、法務省も一体となって翌年「犯罪被害者等基本法」が、さらに翌年「犯罪被害者等基本計画」が策定されました。妻と娘を惨殺された本村氏の執念が司法の壁に穴を開けたと言えるでしょう。
23歳の主婦が強姦され、生後11か月の幼児が18歳の男に惨殺されたこの事件は社会に衝撃を与えました。犯人が少年で被害者が2人なので一審、二審とも判決は無期懲役でした。しかし判決に納得できなかった遺族の本村洋氏の執念の闘いによって9年後、少年に死刑判決が下されました。また被害者の人権も大きく改善されることになったのです。
当時は法廷に被害者の遺影を持ち込むこともできず、遺族が意見を言うこともできませんでした。裁判とは裁判官と検察と被告がやるもので法廷では遺族は完全に部外者扱いでした。しかし「光市母子殺害事件」をきっかけに「全国犯罪被害者の会(あすの会)」ができ、全国に支援の輪が広がりました。2000年には遺族傍聴席の確保、公判記録を閲覧・コピーする権利、公判での意見陳述権を認めた「犯罪被害者保護法」が成立しました。
2003年7月、「あすの会」代表は39万63人の署名を持って小泉純一郎首相に面会しました。小泉首相のリーダーシップの下、法務省も一体となって翌年「犯罪被害者等基本法」が、さらに翌年「犯罪被害者等基本計画」が策定されました。妻と娘を惨殺された本村氏の執念が司法の壁に穴を開けたと言えるでしょう。
名誉毀損で訴えられたジャーナリストが勝つことはほとんどないそうですね?
私たちは学校で「三権分立」という言葉を習います。三権=立法、司法、行政はそれぞれ独立している、という意味です。しかし本来は守られているはずの司法の独立が危うくなっています。それは名誉棄損で訴えられたジャーナリストがほとんど勝てない、という状況に現われています。
薬害エイズは500人以上の犠牲者を出した戦後最大の薬害事件です。その被害者である血友病患者をジャーナリスト、櫻井よし子が取材して証言をまとめた『エイズ犯罪 血友病患者の悲劇』(中央公論社)という本があります。櫻井氏はこの本の中でエイズ研究班の班長であり、血友病の権威であった安倍英(たけし)の責任を厳しく追及しました。それに対して安倍氏は名誉棄損だとして1996年に訴訟を起こしました。そして一審では櫻井氏が勝ったものの、二審では櫻井氏が全面敗訴したのです。
法務省の中には裁判官が就くポストがいくつかありますが、この裁判を担当した大藤裁判長は1995年から97年まで法務省の人権擁護局長だった人物です。当時、政治家の中にマスコミやジャ―ナリストの報道を規制しようという動きがあり「人権擁護推進審議会」が作られたりしました。このようなポストに就く裁判官は国の方針に無条件に従う官僚裁判官です。国はそのような裁判官をわざとこの裁判の担当に振っているのですから、櫻井氏に最初から勝ち目はなかったでしょう。これでは裁判というのはやる前から結論が決まっているのではないか、と疑わざるを得ません。
薬害エイズは500人以上の犠牲者を出した戦後最大の薬害事件です。その被害者である血友病患者をジャーナリスト、櫻井よし子が取材して証言をまとめた『エイズ犯罪 血友病患者の悲劇』(中央公論社)という本があります。櫻井氏はこの本の中でエイズ研究班の班長であり、血友病の権威であった安倍英(たけし)の責任を厳しく追及しました。それに対して安倍氏は名誉棄損だとして1996年に訴訟を起こしました。そして一審では櫻井氏が勝ったものの、二審では櫻井氏が全面敗訴したのです。
法務省の中には裁判官が就くポストがいくつかありますが、この裁判を担当した大藤裁判長は1995年から97年まで法務省の人権擁護局長だった人物です。当時、政治家の中にマスコミやジャ―ナリストの報道を規制しようという動きがあり「人権擁護推進審議会」が作られたりしました。このようなポストに就く裁判官は国の方針に無条件に従う官僚裁判官です。国はそのような裁判官をわざとこの裁判の担当に振っているのですから、櫻井氏に最初から勝ち目はなかったでしょう。これでは裁判というのはやる前から結論が決まっているのではないか、と疑わざるを得ません。
死刑判決が出ても、実際にはあまり執行されていないようですが?
死刑が確定しても執行するためには法務大臣がハンコをつくことが必要です。しかし最近、死刑廃止論者が法務大臣になることが続き、死刑が執行されないという事態になっています。現法務大臣の江田五月も前法務大臣の千葉景子も死刑廃止論者です。江田五月氏は「死刑は欠陥を抱えた刑罰だ。どうせ人間はいつか死ぬんだから、わざわざ死刑にしなくたっていいじゃないか」と発言しています。
個人的に死刑に反対するのはもちろん自由ですが、法務大臣という立場にありながらこういう発言をするとはあまりにも無責任です。死刑制度は社会の秩序を保つための抑止力という側面もありますが、被害者や遺族の「仇を討ちたい」という気持ちを委託された国家が被害者に代わって犯人を罰するものだからです。世論調査によれば、国民の約8割が死刑存続に賛成しています。現行刑法に死刑があるのに、自分の感情だけで死刑執行にハンコをつかない法務大臣は刑法を無視し、法を捻じ曲げていることになります。
「死刑は欠陥を抱えた刑罰だ」というのは、おそらく冤罪が起きる可能性のことを言っているのでしょう。もちろん無実の人が死刑になるなどということは絶対に許されることではありません。しかし、冤罪が起きるのは捜査や裁判のやり方に問題があるからであって死刑そのものに欠陥があるわけではありません。論理をすり替えています。冤罪が起きないように捜査・裁判の精度を高めるように努力するのが法務大臣の仕事ではないでしょうか?
個人的に死刑に反対するのはもちろん自由ですが、法務大臣という立場にありながらこういう発言をするとはあまりにも無責任です。死刑制度は社会の秩序を保つための抑止力という側面もありますが、被害者や遺族の「仇を討ちたい」という気持ちを委託された国家が被害者に代わって犯人を罰するものだからです。世論調査によれば、国民の約8割が死刑存続に賛成しています。現行刑法に死刑があるのに、自分の感情だけで死刑執行にハンコをつかない法務大臣は刑法を無視し、法を捻じ曲げていることになります。
「死刑は欠陥を抱えた刑罰だ」というのは、おそらく冤罪が起きる可能性のことを言っているのでしょう。もちろん無実の人が死刑になるなどということは絶対に許されることではありません。しかし、冤罪が起きるのは捜査や裁判のやり方に問題があるからであって死刑そのものに欠陥があるわけではありません。論理をすり替えています。冤罪が起きないように捜査・裁判の精度を高めるように努力するのが法務大臣の仕事ではないでしょうか?
「裁判員制度」はなぜ導入されたのですか?
これまで見てきたように日本の裁判官には残念ながら社会正義を実現してくれることをあまり期待できません。ですから私たち国民が裁判に関心を持ち、裁判を監視しなければならないことは事実です。そういう意味では「裁判員制度」導入は日本の司法を変える一つのきっかけになるかも知れません。
しかし「裁判員制度」が導入されたのは実はアメリカの要求によるものです。1994年以来、アメリカ政府は毎年10月に「年次改革要望書」というものを日本政府に突き付けてきています。さまざまな産業ごとにアメリカ政府の日本政府に対する規制緩和や構造改革などの要求事項がびっしりと書きならべられた文書です。名前こそ「要望書」ですが実際は「命令」と言えるものでしょう。この中に「司法制度の改革」があります。
「司法制度の改革」でアメリカは日本の裁判は判決が出るまでに時間がかかり過ぎると主張して、裁判の迅速化を要求しています。これは日本国民も望むところでしょう。また裁判官や弁護士の人数を増やすことを要求しています。これは「法科大学院」という、アメリカ型のロースクール制度が2004年4月から日本に導入されたことで実現しました。しかし、なぜアメリカは日本の司法制度改革にこれほどまでに熱心なのでしょうか?
アメリカ政府の真意にはまだ不明な部分もありますが、はっきりしているのは日本をアメリカ型の訴訟社会に改造し、それによってアメリカ企業やアメリカ人弁護士の利益を図ろうとしているということです。もともとアメリカという国は日本とは比べ物にならないほど司法の力が強い国です。かつてのクリントン政権は主要閣僚がすべて弁護士出身でした。ヒラリー・クリントンももとは弁護士です。おそらく「裁判員制度」導入は国民が裁判に直接参加することで日本人がもともと持っている裁判に対する抵抗感をなくさせようとしたものでしょう。
参考文献:関岡英之『拒否できない日本―アメリカの日本改造が進んでいる』(文春新書)
門田隆将『裁判官が日本を滅ぼす』(新潮文庫)
門田隆将『なぜ君は絶望と闘えたのかー本村洋の3300日』(新潮文庫)
しかし「裁判員制度」が導入されたのは実はアメリカの要求によるものです。1994年以来、アメリカ政府は毎年10月に「年次改革要望書」というものを日本政府に突き付けてきています。さまざまな産業ごとにアメリカ政府の日本政府に対する規制緩和や構造改革などの要求事項がびっしりと書きならべられた文書です。名前こそ「要望書」ですが実際は「命令」と言えるものでしょう。この中に「司法制度の改革」があります。
「司法制度の改革」でアメリカは日本の裁判は判決が出るまでに時間がかかり過ぎると主張して、裁判の迅速化を要求しています。これは日本国民も望むところでしょう。また裁判官や弁護士の人数を増やすことを要求しています。これは「法科大学院」という、アメリカ型のロースクール制度が2004年4月から日本に導入されたことで実現しました。しかし、なぜアメリカは日本の司法制度改革にこれほどまでに熱心なのでしょうか?
アメリカ政府の真意にはまだ不明な部分もありますが、はっきりしているのは日本をアメリカ型の訴訟社会に改造し、それによってアメリカ企業やアメリカ人弁護士の利益を図ろうとしているということです。もともとアメリカという国は日本とは比べ物にならないほど司法の力が強い国です。かつてのクリントン政権は主要閣僚がすべて弁護士出身でした。ヒラリー・クリントンももとは弁護士です。おそらく「裁判員制度」導入は国民が裁判に直接参加することで日本人がもともと持っている裁判に対する抵抗感をなくさせようとしたものでしょう。
参考文献:関岡英之『拒否できない日本―アメリカの日本改造が進んでいる』(文春新書)
門田隆将『裁判官が日本を滅ぼす』(新潮文庫)
門田隆将『なぜ君は絶望と闘えたのかー本村洋の3300日』(新潮文庫)